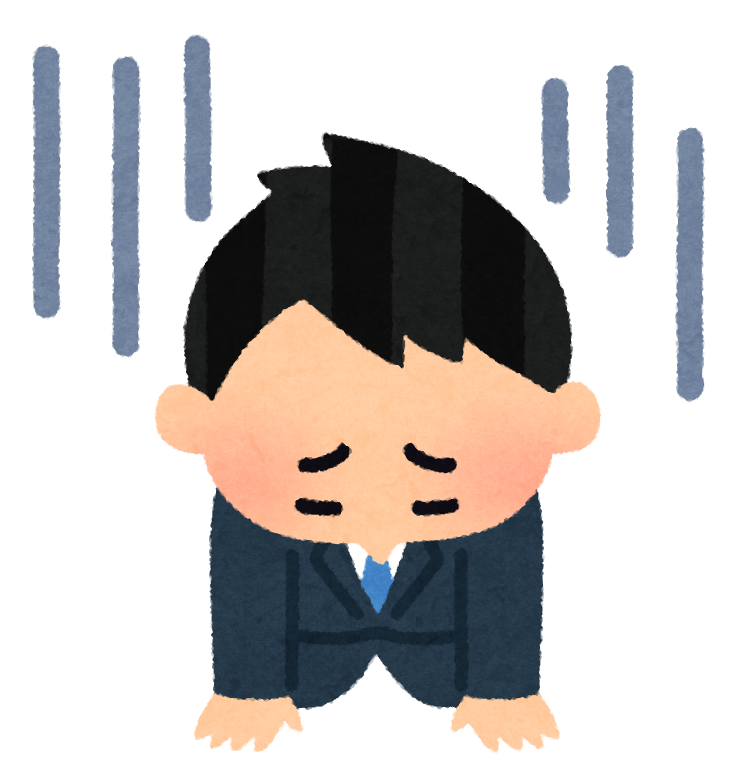建築施工管理を辞めたいと思った時に、「転職せずに我慢すべきなのか?」「他の会社に転職すべきか?」「資格はすてて、他業界に転職すべきなのか?」と悩む方も少なくありません。そこで、今回は辞めたいと思った時に、どうしたらいいのかヒントになる3人の実際の体験談について共有させていただきます。
実際に建築施工管理を辞めたいと思っても、上司に言えず自殺してしまったり、うつ病になるまで無理をしてしまって働けなくなってしまったという方もいます。
あなたが、同じような過ちを犯さないように、建築施工管理を辞めたいと思った時に読んでほしい3人の体験談をお伝えしたいと思います。もし少しでも無理しているなと感じたら逃げる勇気が必要だということを少しでも感じていただけると嬉しいです。そこで今回は建築施工管理を辞めたい理由ランキングと、実体験についてご紹介させていただきます。
建築施工管理を辞めたい4つの理由

建築施工管理をやめたい理由としては、大きく4つあげられます。①休みが取れずプライベートの時間をもつことができない。②慢性的な人手不足で、管理仕事なのに現場仕事をしなくてはいけない。③現場の方や、建築業界の人と人間性が合わない。④建築施工管理は激務なのに、その割に給与が安いといったことが挙げられます。
1.休みが取れずプライベートの時間を持つことができない。
建築業界では、朝から晩まで働きます。そして基本日曜日はやすみなのですが、それでさえ休みが取れずに14連勤、21連勤したという先輩の話もききます。当たり前ですがこれだけ激務であれば、プライベートの時間をもつことができず友達や恋人と時間を過ごせなくなります。
なんのために生きているのかと自分の人生も不安にもなってきます。実際に月間100時間残業時間が超えてしまってもとくに珍しいことでもないので、当たり前として許容される文化があります。
突発工事の発生により、休日に突如出勤しなくてはないけないというこもありますよね。大変なお仕事です。
2.管理仕事なのに、現場で雑用をしている
建築施工管理は管理するのがお仕事ですが、建築施工は建設ニーズが高まっておりどこもかしこも人手不足な状況です。そのため建築施工管理さんでも現場にでたり、新人であれば現場でのゴミ拾いや雑用をすることもあります。
材料や道具を職人と一緒にはこんだり、管理といっても現場管理は外に出て行うので、真夏の猛暑の中外にいなくてはなりません。そういったことを続けるのは体力的に厳しいお仕事でもあります。
3.建築業界の人との人間関係
建築施工管理は高卒の方も多く、”おい、ぼけ!しっかり働けや””、”ぼけっとしてんじゃねー、小僧”といった言葉が平気で飛び交うような職場です。どこの職場もそういうわけではないですが、比較的率直なものいいをする方が多いです。
建築現場は命にも関わる現場もあるためピリピリしていることもあり、そういった中で様々な職人さんとコミュニケーションをとることが求められますが、そういったことが得意な方ばかりではないので、苦手な方はそれが原因で辞めてしまいます。
4.激務の割に給与がやすい
建築施工管理はサービス残業がおおいです。100時間働いても会社によっては40時間までしか出さない等の暗黙のルールがあったりします。年収自体は全体の平均年収よりも高い462万ですが、実際の労働時間を鑑みれば時給単価では全体の底辺までいってしまうでしょう。
給与が全てとはいいませんが、努力が報われないことが多く嫌気がさしてしまう方も多いです。そのような環境ではなかなか家族の理解を得られず家庭を築くのが難しいですからね。
実際に建築施工管理技士を保有しているかたは800万以上出ている会社も少なくありません、適切な会社ではたらくことが大事です。
辞めたいけど辞められない」人が抱える不安やリスク
会社や現場に与える影響(後任がいない、プロジェクトの途中で辞めにくい等)
(1) 後任不在のリスク
- 具体例:
- 現場監督が1名体制で回している小~中規模の現場の場合、退職後に後任が見つかるまで現場が止まる可能性がある。
- 大手ゼネコンであっても、現場が多岐にわたって人手不足のケースがあり、「今は抜けられない」と引き止められることが多い。
- 影響:
- 会社にとっては工期遅延や追加コストが発生するリスク。
- 自分自身も「責任を感じて辞めづらい」という精神的な負担が増しやすい。
(2) プロジェクト途中での退職
- 具体例:
- 大型商業施設の新築工事で、工事全体の30%ほど完了した段階で辞めたいと思っても、上司やクライアントに「最後までやり遂げてほしい」と言われることが多い。
- 途中退職すると、工事監理や品質管理上の情報引き継ぎが十分に行われない危険性がある。
- 対応策:
- 早い段階で退職意向を上司に伝え、引き継ぎマニュアルを作成するなどして現場が混乱しないよう準備を進める。
- 後任候補者に現場状況や顧客とのやり取り状況を詳しく共有し、退職後のトラブルを最小限に抑える。
(3) 円満退職を目指すために
- 具体例:
- 「プロジェクトが○○%進捗したら退職する」という明確な時期を伝える。
- 例えば躯体工事が完了した時点や、主要な発注作業が一段落したタイミングなど、プロジェクトの区切りがはっきりしている箇所で辞めると、会社側も受け入れやすい。
- メリット:
- 円満退職により、会社との関係を悪化させずに済む。将来的に業界内で再会する可能性も考慮すると、トラブルを避けるのが得策。
自分のキャリア(もし建築施工管理を辞めたら、その後の仕事はどうなる?)
(1) 建設業界内でのキャリアチェンジ
- 具体例:
- ゼネコンの現場監督から、同じ会社の設計部門や積算部門に異動。
- デベロッパー企業へ転職し、工事発注側としてプロジェクト管理に携わる。
- メリット:
- 建築施工管理で培った現場経験やコミュニケーション力が活かせる。
- 設計段階での実務感覚があることで、現場目線の提案ができる。
(2) 全く別の業種・職種への転職
- 具体例:
- IT系へキャリアチェンジし、プロジェクトマネージャーやシステムエンジニアなどに転身。
- 異業種の営業職として、建築関連の知識を活かしながら新しい分野を開拓する。
- 考慮すべき点:
- 未経験業種の場合、一から学ぶ必要があり、即戦力としての期待値が低くなる可能性がある。
- 年収や待遇面が一時的に下がるリスクを受け入れるかどうかが分かれ目になる。
(3) フリーランス・個人事業主として働く
- 具体例:
- 協力会社や設計事務所など、複数のクライアントと業務委託契約を結んで、特定工程の管理や図面作成を請け負う。
- フリーランスの施工管理技士として、プロジェクトごとに現場を転々とする。
- 注意点:
- 安定した収入を得るためには受注先の確保が重要。人脈作りや営業スキルが必要になる。
- 会社員ほど福利厚生が整っていないため、社会保険や税務処理も自己責任。
(4) 自分の将来像を明確にする
- 具体例:
- 「現場経験を5年積んで、将来は自分で設計事務所を立ち上げたい」
- 「短期的には年収が多少下がっても、ストレスの少ない環境で働き、長期的にキャリアアップしたい」
- メリット:
- ゴールやビジョンが明確だと、転職活動もスムーズに進めやすく、後悔しづらい。
- 曖昧なまま辞めると、「辞めたはいいが、次に何をすればいいかわからない」と混乱しやすい。
資格をどう活かすか(1級・2級建築施工管理技士などを他職種で活かせるのか?)
(1) 資格保有のメリット
- 具体例:
- 1級建築施工管理技士を持っていると、監理技術者として現場を任せてもらえるため、転職市場では高い評価を受けやすい。
- 2級でも特定の工事規模や種類によっては現場監督を務められるため、若手から中堅クラスまで需要がある。
- 優遇・手当:
- 資格手当が支給される企業が多い。転職先によっては月1~3万円程度プラスになる場合も。
- 監理技術者として必要とされるため、現場経験+資格があればキャリアの選択肢が広がりやすい。
(2) 他職種での活かし方
- 設計や積算の仕事:
- 施工管理の知識と資格があると、実際の施工費や工期を踏まえた設計プランを立てられるため、設計事務所やゼネコン設計部門で重宝される。
- 建設コンサルタント:
- 公共事業の調査・計画段階から工事監理まで幅広く携わる。資格保有者が多い会社ほど公共案件を受注しやすいため、1級・2級の取得は有利になるケースが多い。
- 不動産関連(デベロッパーや管理会社):
- 建築施工管理の視点で、不動産の価値や建物のメンテナンス計画を立てられる人材は重宝される。マンション管理やリフォーム部門などでも活かせる。
(3) 資格を継続管理する際の注意点
- 登録更新・CPD(継続教育)
- 建築施工管理技士の資格は、定期的に講習や更新手続きが必要になる場合があります。
- 転職後も資格を活かせる職種を選ぶ
- 資格を活かすかどうかで、業務範囲や待遇が大きく異なるため、転職先の業務内容と資格要件をチェックしておくことが大切です。
建築施工管理を辞める前に試してほしいこと
1.社内異動や配置転換を検討(内勤や設計部門などへの異動は可能か)
1. チーム体制の再編成や追加人員の要請
- 大手ゼネコンや中堅以上の会社の場合: 他の現場や部門からの応援要員を一時的にでも確保できないか、上司や総務部門と相談しましょう。
- 中小企業の場合: 外注・派遣を活用できるか、協力会社にサポートを依頼できないか検討してみることも大切です。
- 具体的な提案書作成: 「どのタイミングで・何人必要か」「人員補強によりどのように工期短縮・残業削減が実現するか」を数字で示すと説得力が高まります。
(2) 工期スケジュールの見直しと交渉
- クライアントとのスケジュール再調整: 納期や工期に余裕を持たせられないかを直接交渉し、不可抗力があった場合などは延期や段階的引き渡しの可能性を探ってみます。
- 余裕を作るマイルストーン管理: 「○月○日までに○○を完了させる」という詳細なマイルストーンを設定することで、計画の“詰め込みすぎ”を防ぎやすくなります。
- 根回し・関係性づくり: 工期延長の相談は早めに行うことが鍵。後手に回るとクライアントとの信頼関係が損なわれる可能性があるため、できるだけ“余裕を持った”提案を。
(3) 生産性向上の工夫
- ICT活用や新工法の導入: 建設業界でもドローンやBIM、クラウド管理ツールなどを活用する事例が増えています。効率化により長時間労働を緩和できる可能性があります。
- 業務の属人化を防ぐ: 施工図の作成や工程管理ソフトの使用方法を周知するなど、特定の担当者に過度な負担が集中しないしくみを整える。
2. 社内異動や配置転換を検討(内勤や設計部門などへの異動は可能か)
(1) 会社の組織構造・部署を把握する
- 大手ゼネコンや総合建設会社には、設計部門、積算部門、営業部門、総務部門など多様な部署があります。
- 異動希望を伝える前に、自分が得意とするスキル(CADが得意、コミュニケーションに強みがある等)を整理しておくと上司に説明しやすくなります。
(2) 「内勤ポジション」や「設計・積算部門」への移動
- 設計や積算に携わる: 施工管理の現場経験を活かし、実際の施工段階を想定した設計や工事費の見積もりに強みを発揮できます。
- 施工管理の知見があるからこそ、設計上の無駄を省いたり、現場が混乱しない図面を作成する“設計者”は会社にとって貴重な存在です。
(3) 「建築施工管理技士」の知識を活かせる事務系ポジション
- 技術営業・工事監理サポート: 技術的なバックグラウンドを活かし、営業や顧客対応に回るケースもあります。
- 総務・人事での安全管理や社内教育: 大手企業の場合、社内研修を担当する専門チームがあり、自身の経験を後輩指導に活かす道も。
(4) 上司・人事部門への相談
- 正式な手順で異動願いを出す: 会社規模によっては定期異動のタイミングが決まっている場合もあるので、その時期を見越して早めに希望を伝えます。
- 異動が難しい場合: 会社としても人材不足で現場を離してくれないケースがあります。その際は妥協策として勤務形態や担当現場を変えてもらえないか交渉を。
3.休職制度・ワークライフバランスの見直し(有給取得や短期休暇の取得)
(1) 有給休暇の取得促進
- 建設業界は特に有給取得率が低い傾向がありますが、法的には一定の有給休暇を取得する権利があります。
- 「忙しさ」を理由に取得を遠慮しない: 現場によっては人手不足で申し訳なさを感じるかもしれませんが、会社や上司が合法的に拒否できるわけではありません。早めに計画的に申請しましょう。
(2) 短期休暇やリフレッシュ休暇の活用
- 会社独自の制度として、連続休暇やリフレッシュ休暇が導入されている場合があります。
- プロジェクトの区切りごとに休みを取る: 現場がある程度落ち着いたタイミングで連休を取れるよう、上司やクライアントとの調整を事前に行うことが大切です。
(3) 長期休職・産業医の利用
- 心身の不調が深刻な場合: メンタルヘルスの問題や身体的に継続が難しい状況なら、「休職」も一つの選択肢です。
- 産業医や健康管理室への相談: 大手企業では産業医と面談の機会を設けることができ、必要に応じて休職の診断書が発行されるケースも。
- 早期発見・早期対応: 放置していると重度の鬱症状や適応障害につながる可能性があるため、早めに休養を取る決断が重要です。
(4) 働き方改革関連法への理解
- 働き方改革関連法により、時間外労働の上限や年5日の有給取得義務化などが定められています。
- 会社のコンプライアンス体制を活用する: 違法な状況がある場合は、総務部門や労働組合へ相談することで会社全体の体制改善を促せるかもしれません。
4. メンタルケア・専門家に相談する(産業医、カウンセリング、キャリアコーチング)
(1) 産業医との面談
- ストレスチェック結果などから、一定水準を超えるストレスが見られる場合は産業医との面談を会社が手配することがあります。
- 面談時に現場の実情を正直に話す: どのような業務負荷があるのか、睡眠や食事の状況、精神的なつらさを具体的に伝えることで、業務軽減や勤務時間の短縮などの具体的指導を受けられる場合があります。
(2) カウンセリングやEAP(従業員支援プログラム)の活用
- 社員用ホットライン: 大手企業だとカウンセラーや外部の専門機関と提携している場合があります。匿名相談できるケースもあるため、遠慮なく利用してみましょう。
- オンラインカウンセリング: 建設業界は現場が遠方になることも多いため、オンラインで専門家とつながれるサービスを活用すると通いやすくなります。
(3) キャリアコーチング
- 職場の外部リソースとして、キャリアコーチやキャリアカウンセラーに相談する方法があります。
- 客観的視点を得る: 第三者の視点で「自分の強み・弱み」「将来像」「転職すべきか継続すべきか」などを整理できるため、今後の方向性を冷静に判断できます。
(4) 家族や友人、同業者コミュニティのサポート
- 一人で抱え込まない: 建設業界特有の働き方やプレッシャーを、家族や友人に十分理解してもらえないかもしれませんが、話すだけで気持ちが軽くなることがあります。
- 同業者コミュニティの活用: オンラインサロンやSNSグループ、勉強会などで同じ悩みを経験している人と意見交換すると、新たな視点や解決策を得られる場合も。
建築施工管理をやめたいと思ったら読む話①

現在30歳です。当時私は建築業界に入って4年目の26歳の時の話です。
私の会社は建築施工管理の入れ替わりも激しく人もたりていないのが日常でしたので派遣の方も多く働いていました。そのため会社の上層部も転職や、いなくなる事を前提に考えており、教育はしなければ、入社してくださったかたへの風当たりもつよかったです。うまく育てば、儲けもん。基本的にはやめても問題ないとの考えでした。
私はまだやる気があり、キャリアアップを考えていましたが、現場は元請けからの指示通りに動くだけ。とても建築施工管理としてスキルアップできるような環境もなく、会社としても提供をしてくれる場所だと感じることができずにおりました。
それでもいつかはキャリアアップするぞ!と意気込んでおりましたが、ある日上司に”お前みたいなはんぱなやつは一生雑用をしていろ”と言われて何かが自分の中で折れてしまいました。
会社に辞めたいと伝える
もう心身疲労し、がんばれないと思い、退職したいと会社に伝えると、”おまえに投資した分を回収できていない”、そのほかにも”人間として終わっている”、”ほかにいっても活躍できるわけないだろ。俺がその転職先にお前の無能さを伝えてやる”と色々な言葉で私の人格を否定してきました。私は会社と家の往復で会社だけが自分の場所になってしまっていたので、上司の言葉が重くのしかかりました。
その日から、朝起きると、頭がいたくて、布団からでられない。家を出ようとすると吐き気を催すようになり、限界へと一歩一歩近づいていました。会社に体調がわるいと連絡すると、上司からは電話越しに、”嘘をつくな、いい加減にしろ”と怒鳴られたことを今でもはっきりと覚えています。
そんな日常が続いたある日のことでした。ふと線路に飛び降りている私がいました。しかしながら側にいたアメフト部の大学生の集団に運良く助けられ無事に事なきをえましたが、そのあと病人に搬送され、重度のうつ病だと診断されました。
死ぬまでやる必要はない
死ぬなんてアホだとおもっていましたが、自分がその立場になってようやくわかりました。会社が全てになっていて逃げる場所もない。プライベートの時間がない中で、側で弱音をはける人もいない。そんな環境ではたった一つの言葉で人を死に追いやってしまうことさえもある。
それでも、今は同じ建築施工管理として働いていますが、充実した日々を過ごしています。休みは日曜日だけですが、それでも平日は定時過ぎには変えることができ、家族との充実した時間も作れています。休みの日にはディズニーに行ったり、熱海にドライブにいったりと前では想像もできなかったような日々です。
建築施工管理を辞めたいと思っているあなたへ
もし建築施工管理を辞めたいと思っている。けれど一歩先にすすめないとおもっていたら、誰かにまずは相談してみましょう。今の時代働く先はいっぱいあります。身近な方、転職エージェントの方、なによりもあなた自身を大切にして、まずは今の状況を客観的に捉えることから初めてみてはいかがでしょうか?
建築施工管理をやめたいと思ったら読む話②

私は、新築、リフォーム工事の現場を中心に働いていました。仕事をしている中で、休日出勤は日常茶飯事でした。夜勤も多く通常23時に帰り、22時で帰れたら今日は早いなーと感じていました。ほとんど毎日が残業続きで、それに対する賃金が非常に安かったです。私の会社では130時間くらい平均残業をしていたと思います。
転職する一番のきっかけは、夜勤業務半年間で手当て等が全く出なかったことです。時間外に毎月130時間も働いて、手当が出ないってどういう会社なんだろうと日に日に不満は募っていきました。こういった会社がいまだに潰れずに存在すること自体が信じられません。
またトラブルも多く、営業の打ち合わせ内容が不十分だったり、打合せ内容の指示・伝達ミスでのクレームなども非常に多かったです。その度に謝るのは私でした。なんで謝らなきゃいけないんだろうといつも思っていました。
現職の建築施工管理をやめて、転職を決めてからは?
転職をすることを決意してからは、社員が全般的に若く、将来性が見込める会社を探していました。また知り合いの会社ということでもあり、勧誘を受けた段階での話では様々なチャレンジが出来そうだと考えました。
具体的には、下請けから元請け(一部、下請け)への転換を目標にしているということで、営業面の強化が課題でした。これまでの現場管理業務のみをこなしていくのとは違い、幅広い業務内容を行い、経験的にも幅を広げることができる、それに伴って賃金のステップアップが図れるということでした。
この業界は下請けがはびこっており、実際にこの負の構造をかえるだけで、もっと正しく人が稼げるのにと思っていました。2次受け、3次受けがなくなっていき、元受けとして正しく受注をできるように多くの会社がなり、統廃合されていけばよりよい業界になるのにと思っています。
そういった意味でもM&Aを積極的にされている会社に関しても魅力的に見ています。自分の会社から1歩外へでてみると魅力的な会社がいっぱいあって、現状に不満をかかえていたら自分の価値を客観的にみてみるのがいいと思います。あなたの価値を理解して発揮させてくれる会社で働けることを祈っております。
建築施工管理をやめたいと思ったら読む話③

37歳の時に前々職の仕事から大きく方向転換をして転職をしましたが、独立できるだけの自信を付けて、自分のやってみたいことに挑戦をしようと考えました。
▶ 関連記事: 【2025年版】ゼネコンとサブコンの違いを徹底解説!建設業界で活躍するために知っておくべきポイント
41歳で結婚したのもあり、42歳で時間面や給与面を考慮して転職をしました。人伝での転職で、1社のみとの話合いで、正式な面接は行っていません。現場で退職の意向を雑談的に話をし、現場で勧誘されて、夕食をかねて条件面や会社の方向性等について話し合いを社長と一回だけ行いました。
転職で給与が下がった
給料面は50万円程下がりました。食事の際の条件面の話し合いで、当面ということで暫定的に決めたものではありますが、経営状態からいうとしばらくは満足のいく給与ということにはなりそうもありません。転職活動として多くの時間を割いたことはなかったので、仕事との両立は可能でした。
会社をもう少し研究してから転職すべきだとは思いました。人伝のような形での転職よりも、転職の専門家というか、コンサルタントのような方が間に入って下さる方が、そのあたりの対策がしっかりできているのだろうとも思います。
縁故採用で失敗した
外部から接していたのとは知り合いだったとはいえ、大きく印象が異なりました。社員全員に対して、雇ってやっているんだという意識が強く、自分に従うのが当然だという考え方のようなのですが、人材、とくに若い人材を大切にする、育てて行くという考えが希薄すぎる気がします。
また大きな利益は出ていないのですが、そのあたりでも気持ちに余裕が無いようだとか、内情はなかなか分かりにくいもので、知り合いでも分からない部分を何度かの面接等で判断するというのは非常に難しいだろうと思います。
会社の内情をしっかりと調べないと後悔する
難しいことだとは思いますが、経営状態や時間管理の仕方等は、内部に入ってみなければ分からないことなので、そういった情報が少しでもあれば良かったと思います。給料が時給換算するといくらになるのかも、指標としては確認できればいいかなと思います。時給にするといくらなのかを考えたとき、コンビニでアルバイトするよりも安い給料だったと若い社員の子が言っていたのですが、確かに今の自分で考えてみても、時給換算で非常に生産性の悪い働き方、余裕がない生活を送っているなと思います。
転職で良かったことはあまりなかったかもしれません。とくに中小企業ということになると、時間をどれだけ長く働かせるかと考えている経営者が多いのではないかと思うようになってきましたが、そのあたりは外部から接しているだけでは判断できない部分が多々あると思います。
専門のコンサルタント的な方などを介すのは、そういった部分で有効かなとは今回の転職で感じました。現場管理の仕事というのは、内容的にはある程度似たようなところもあるでしょうし、時間の管理の仕方などは、経営者の考え方ひとつといったところもあると思います。
1. 施工管理職でも中小~大手で働き方が違う
(1) 大手ゼネコンや大手工務店の特徴
- 扱う案件規模: 大規模マンション、商業施設、インフラ(道路や橋など)といった大型案件が中心。
- 組織体制: 一つの現場に複数人の施工管理者がおり、役割分担が細かく決められている。
- メリット:
- 福利厚生や研修制度が充実している。
- 大規模案件でスキルを積める。
- 1級施工管理技士などの資格取得支援制度が整っている場合が多い。
- デメリット:
- プロジェクトの規模が大きい分、工期がタイトで残業が増えやすい。
- 下請け業者や関係部署が多く、調整・書類業務に追われることも。
(2) 中小の工務店・建設会社の特徴
- 扱う案件規模: 戸建住宅や小規模集合住宅、地域の公共施設などがメイン。
- 組織体制: 少人数で複数の業務を兼任することが多い(施工管理+営業+顧客対応など)。
- メリット:
- 個人の裁量が大きく、経営層との距離が近い。
- 幅広い業務スキルが身につきやすい。
- デメリット:
- 人員不足で休日や有給が取りにくい場合も多い。
- 組織体制が整っていないと、現場負担が集中してしまいやすい。
転職のポイント: 「大手の充実した組織の中で働きたいか、あえて小規模でスピード感ある環境を選ぶか」で、働き方やワークライフバランスが大きく変わります。
▶ 関連記事: 【設備管理とは?】業務内容・必要な資格・将来性を徹底解説
2. デベロッパー、ハウスメーカー、設備系企業、建設コンサルタント、設計事務所など
(1) デベロッパー(開発会社)
- 業務内容: 土地取得、企画・開発、販売まで一貫して行う。大規模マンションや商業施設のプロジェクトを主導。
- 施工管理経験が活きる場面:
- 設計段階での工法検討やコスト算出。
- 現場を管理するゼネコンや設計事務所との折衝。
- メリット・魅力:
- 現場だけでなく、企画や事業推進の上流工程に関われる。
- 土地活用や都市開発の視点が身につき、キャリアの幅が広がる。
- 注意点:
- 開発スケジュールが厳しい場合もあり、案件によっては残業が発生しやすい。
- 不動産市況の影響を受けやすく、景気変動によるリスクも。
(2) ハウスメーカー
- 業務内容: 戸建住宅や注文住宅の設計・施工・販売がメイン。
- 施工管理経験が活きる場面:
- 設計との打ち合わせや顧客へのプラン説明で、現場を踏まえたアドバイスができる。
- 現場監督として品質・納期を管理する業務もあるが、営業との連携も重要。
- メリット・魅力:
- 個人顧客との直接的なやり取りでやりがいを感じやすい。
- 比較的、狭い範囲の工事でプロセスが見通しやすい場合が多い。
- 注意点:
- 大手ハウスメーカーの場合、ノルマや顧客対応で精神的負担が大きくなることも。
- 住宅業界は繁忙期(引越しシーズンなど)の残業が増えがち。
(3) 設備系企業(空調・衛生・電気設備など)
- 業務内容: 建築物の空調、給排水、電気設備などを設計・施工。
- 施工管理経験が活きる場面:
- 建築本体工事と設備工事の調整や、図面上での干渉チェックなどに強みを発揮。
- サブコン(設備専門の施工会社)で活躍すると、建築と設備の両面に通じた人材として重宝される。
- メリット・魅力:
- 設備分野に精通すると、建築・電気・機械といった幅広い技術を身につけられる。
- 今後も空調やエコ関連技術の需要は高まる見込み。
- 注意点:
- サブコン業界も人手不足で、繁忙期には残業や休日出勤が増える場合がある。
- 現場仕事が苦手な人は、設計やメンテナンス部門への異動を検討してみるとよい。
(4) 建設コンサルタント
- 業務内容: 公共事業や土木・インフラ整備の計画・調査・設計が中心。橋梁や道路、上下水道などの社会基盤整備を行う。
- 施工管理経験が活きる場面:
- 実際の施工現場を知っていることで、より現実的な設計や工法提案ができる。
- 発注者支援業務(発注図書の作成や工事監理補助)で実務感覚が評価されやすい。
- メリット・魅力:
- 公共事業に携わるため、景気に左右されにくい安定した案件が多い。
- 設計やコンサル業務がメインの場合、現場常駐に比べ労働環境が比較的落ち着きやすい。
- 注意点:
- 会社によっては資格や経験がないと即戦力になりづらい部分も。
- 公共案件の書類作業が膨大になる場合があり、繁忙期には負担が増えることも。
(5) 設計事務所
- 業務内容: 建築の基本・実施設計、意匠設計、構造設計など多岐にわたる。
- 施工管理経験が活きる場面:
- 現場の施工プロセスを把握していることで、実践的かつコストダウンしやすい設計が可能。
- 施工図や詳細図の作成で「現場が施工しやすいか」を考慮できる。
- メリット・魅力:
- デザイン性や創造性を追求できる案件も多く、モノづくりの喜びを味わえる。
- 技術的チャレンジやアート性の高い建築など、やりがいを感じやすい。
- 注意点:
- 設計業務はクライアントや施工会社との打ち合わせが多く、納期前の残業は発生しやすい。
- 設計事務所によっては収益構造が厳しく、給与水準が低めになる場合もある。
3. 公共事業関連の事務職や建築審査機関(確認検査機関)
(1) 公務員や自治体関連の事務職
- 業務内容: 建築確認や都市計画、公共施設の保守管理など。
- 施工管理経験が活きる場面:
- 現場知識があると、住民や事業者への説明、工事許可手続きの判断が的確にできる。
- 公共施設の改修や点検計画策定で、施工管理経験者が頼りにされやすい。
- メリット・魅力:
- 比較的安定した雇用と給与体系、休日・福利厚生が充実している。
- 地域社会のインフラ整備に貢献できる達成感がある。
- 注意点:
- 公務員試験や資格が必要な場合がある。転職のハードルがやや高いケースも。
- 予算編成の時期など、繁忙期は多忙になりやすい。
(2) 建築審査機関(確認検査機関)
- 業務内容: 建築基準法などに基づき、建築物の図面や仕様を審査・確認する。
- 施工管理経験が活きる場面:
- 図面上での法令遵守や安全面をチェックする際、現場視点があると問題点を発見しやすい。
- 実際の施工方法とのギャップを早期に把握でき、適切なアドバイスを行える。
- メリット・魅力:
- 現場常駐の必要がなく、比較的落ち着いたオフィスワークが中心。
- 法令知識が身につきやすく、建築全般の専門性が高まる。
- 注意点:
- 取り扱う案件数が多い場合、審査・書類チェックに時間を要することも。
- しっかりした法的知識や資格(建築士など)が求められるケースも多い。
4. 施工管理技士資格を活かしたフリーランス・派遣の可能性
(1) フリーランス施工管理の働き方
- 業務内容: 協力会社や建設企業と業務委託契約を結び、期間限定またはプロジェクトベースで現場管理を担当。
- 具体例:
- 大手ゼネコンの下請けとして、一定期間だけ施工管理・現場監督を引き受ける。
- 特定の工程のみ(仕上げや安全管理など)専門でサポートする。
- メリット:
- 複数のクライアントからの依頼を受け、自由度の高い働き方が可能。
- 高単価案件を獲得できれば、会社員時代よりも年収アップする場合も。
- デメリット:
- 案件が途切れるリスクがあるため、安定収入が得にくい。
- 福利厚生や社会保険は自分で手配する必要がある。
- 営業や契約管理、経理処理など、施工管理以外の業務にも時間を割かれる。
(2) 派遣社員として働く
- 業務内容: 派遣会社に登録し、派遣先の建設現場で施工管理補助や工程管理を行う。
- メリット:
- 希望の勤務地や期間に合った仕事を選びやすい。
- 大手企業の現場に派遣される場合、スキルアップや大規模案件の経験が積める。
- デメリット:
- 派遣期間が終了すると、また別の案件を探す必要がある。
- 会社員としての安定した雇用形態ではないため、福利厚生やキャリアパスが限定されやすい。
(3) 注意点と心構え
- 資格の更新やスキル維持: フリーランス・派遣でも定期的に研修や講習を受け、資格や技術のアップデートが必要。
- ネットワークづくり: 安定して案件を確保するには、人脈や実績が重要。現場での評判が次の仕事につながるケースが多い。
- 自己管理能力: スケジュール調整や契約条件の交渉、社会保険・税務処理などを一手に引き受ける覚悟が求められる。
終わりに
いかがだったでしょうか?
施工管理だからといってどこの会社もかしこもブラックというわけではありませんし、環境を変えることで上手くいくこともあります。そのため、今の環境があなたにとって厳しい環境であれば、体を壊すまで無理をするまえに、会社外の周りの人に相談してみてはいかがでしょうか?
自分の会社しか知らなければ、その他の会社のことがわからないので、ぜひ知ることからスタートしましょう。下記から無料の相談も行なっているので気軽に相談ください!
建築施工管理が「きつい」と言われる業界の現実
建築施工管理が「きつい」と言われる理由は、単なる仕事の忙しさだけではありません。厚生労働省の調査によると、建設業の労働時間は全産業平均より年間約300時間も長く、週休2日制の導入率も他業界と比べて大幅に低い状況が続いています。
労働環境の厳しさを示すデータ
国土交通省の建設業働き方改革の調査では、以下のような実態が明らかになっています:
- 月80時間以上の残業をしている建築施工管理者が全体の約40%
- 年間休日が105日未満の会社が建設業界の60%以上
- 建設業の離職率は他業界平均の1.5倍以上
- 精神的疾患による休職者の割合が他業界の2倍
現場で直面する具体的な「きつさ」
建築施工管理者が日常的に経験する「きつさ」は多岐にわたります。朝7時から現場に出て、夜10時過ぎまで事務作業を続けることも珍しくありません。さらに、以下のような状況が重なることで、心身への負担は増大します:
- 複数現場の掛け持ち:人手不足により1人で2〜3現場を同時管理することも
- 突発的なトラブル対応:天候不良、資材の遅配、近隣からのクレーム処理
- 板挟み状態:発注者からのコスト削減要求と現場の安全確保の両立
- 責任の重さ:工期遅延や事故が発生した場合の個人責任
実際の現場では、施工管理者が本来の管理業務だけでなく、作業員の手伝いや清掃作業まで行うケースも多く、「管理職なのに現場作業員と同じことをしている」という状況が常態化しています。
心身への影響と健康問題
建設業労働災害防止協会の調査によると、建築施工管理者の約70%が慢性的な疲労を感じており、30代で既に体調不良を訴える人が急増しています。具体的な症状として以下が報告されています:
- 慢性的な睡眠不足(平均睡眠時間5時間未満が約45%)
- 腰痛・肩こりなどの身体的症状(約80%が経験)
- 精神的ストレスによる不眠やうつ症状(約25%)
- 家族との時間確保の困難(週末出勤率約60%)
特に深刻なのは、これらの過酷な労働環境が「建設業界では当たり前」として受け入れられてしまっている点です。新入社員の約30%が入社3年以内に離職しており、「きつい」環境への適応を求められる文化が根強く存在しています。
なぜ建築施工管理は「やめとけ」と言われるのか
建築施工管理に対して「やめとけ」という声が多く聞かれる背景には、業界構造的な問題と個人のキャリア形成への影響があります。建設業界経験者や転職エージェントからも頻繁に聞かれるこの言葉には、具体的な理由があります。
キャリア形成への悪影響
建築施工管理を「やめとけ」と言われる最大の理由は、長期的なキャリア形成に与える悪影響です。以下のような問題が指摘されています:
- スキルの汎用性の低さ:建設業界特有の知識・経験で、他業界転職時に評価されにくい
- 学習時間の確保困難:長時間労働により新しいスキル習得の時間がない
- 人脈形成の限界:業界内の狭い人間関係に限定される
- 年収の頭打ち:管理職になっても他業界と比較して給与水準が低い
業界の構造的問題
転職市場調査では、建築施工管理経験者の転職成功率は他の技術職と比較して約20%低いというデータがあります。これは業界特有の以下の構造的問題が影響しています:
下請け構造による責任の集中:元請け・下請けの多層構造により、施工管理者に過度な責任が集中します。工期の遅れや品質問題が発生した場合、現場の施工管理者が矢面に立たされることが多く、精神的負担は計り知れません。
労働環境の改善が進まない現実:建設業界全体で働き方改革が叫ばれていますが、実際の現場では旧態依然とした労働慣行が続いています。週休2日制の導入が進まず、2024年から適用される時間外労働の上限規制への対応も遅れている企業が多数存在します。
経験者からの具体的な警告
建築施工管理を経験した転職者からは、以下のような声が多く聞かれます:
- 「30代で体を壊し、転職活動も困難になった」(元現場監督・35歳)
- 「資格は取得できたが、プライベートを完全に犠牲にした」(元施工管理・29歳)
- 「他業界への転職で年収が大幅にダウンした」(元工事主任・32歳)
- 「家族との時間が取れず、離婚を経験した」(元現場代理人・38歳)
若手人材への特別な警告
特に20代の若手に対して「やめとけ」と言われる理由は、キャリアの可塑性が高い時期を過酷な労働環境で消費してしまうリスクにあります。人材育成の専門家によると、20代で身につけるべき以下のスキルを習得する機会が制限されます:
- ITスキルやデジタルリテラシーの向上
- 論理的思考力やプレゼンテーション能力の開発
- 幅広い業界知識と人脈の構築
- ワークライフバランスを保った働き方の習得
ただし、建築施工管理にもメリットはあります。国家資格取得による専門性の証明、社会インフラ構築への貢献実感、比較的安定した雇用などです。しかし、これらのメリットと引き換えに失うものが多すぎることから、多くの経験者が「やめとけ」という警告を発しているのが現実です。